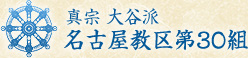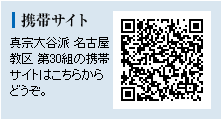- ホーム >
- 交流する
同朋会運動
真宗同朋会運動について
真宗同朋会運動とは、1962年(昭和37年)に「真宗門徒一人もなし」という真宗大谷派の自己批判から始まった信仰復興運動です。
日本の社会は昭和30年代に入ると戦争による傷も少しずつ癒え、高度経済成長期に入り始めます。社会の構造は目を見張るスピードで変化し、寺院をとりまく環境も大きく変化した時代でした。
特に人口の流動化は著しく、過疎・過密という問題が表面化し始めます。田舎では都会へ出て行く若者がふえ、地域の伝統や習慣を維持していくことすら難しくなり、逆に都会では人口の増加と共に、隣に住んでいる人の顔さえわからないという程、地域の結びつきが希薄になっていった時代でした。
高度経済成長は各家庭の経済状況にも大きな変化をもたらしました。白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫を「三種の神器」と呼び、その後はカラーテレビ・クーラー・自動車を「新三種の神器」と呼ぶなど、人々は地域の伝統や習慣を大事にしていた意識から、「消費は美徳」と評されるような、各種の物質を手に入れることに人生の喜びを感じるような意識へと時代と共に変化していきました。
また、この時代は宗教界にも大きな変化がありました。日本における第2期宗教ブームと呼ばれた時代で、いわゆる新興宗教が大きくその勢力を拡大した時代でもありました。
真宗大谷派はこのような大きな社会の変化の波に飲み込まれた中で、1961年(昭和36年)に親鸞聖人の七百回御遠忌を迎えようとしていました。その5年前の1956年(昭和31年)に宗務総長名で出された『宗門各位に告ぐ(宗門白書)』には「この憂うべき宗門の混迷は、どこに原因するのか。宗門が仏道を求める真剣さを失い、如来の教法を自他に明らかにする本務に、あまりにも怠慢であるからではないか。今日宗門はながい間の仏教的因習によって、その形態を保っているにすぎない現状である。寺院には青年の参詣は少なく、従って青壮年との溝は日に日に深められているのではないか。厳しく思想が対立し、政治的経済的な不安のうずまく実際社会に、教化者は、決然として真宗の教法を伝道する仏法者としての自信を喪失しているのではないか。寺院経済は逼迫し、あやしげな新興宗教は、門信徒の中に容赦なくその手をのばしてきている。教田の荒廃してゆく様は、まさに一目瞭然であるが、われらは果たしてこの実情を、本当に憂慮し、反省しているであろうか。」とあります。
この文章からわかるように、地域社会の結びつきと、伝統や習慣を大事にしていこうとする人々により継承されてきた寺院の基盤は、社会構造や価値観の変化により音をたてて崩れはじめ、新興宗教の攻勢の前に、「仏道を求める真剣さを失い、如来の教法を自他に明らかにする本務に、あまりにも怠慢」であった宗門は為す術もなく、門信徒が新興宗教に流れていくことを留めることも出来ずにいました。
そのような危機的状況のなか親鸞聖人七百回御遠忌は厳修され、その翌年の1962年(昭和37年)に真宗大谷派の機関誌である『真宗』の巻頭言で「真宗同朋会とは、純粋なる信仰運動である。それは従来単に門徒と称していただけのものが、心から親鸞聖人の教えによって信仰にめざめ、代々檀家と言っていただけのものが、全生活をあげて本願念仏の正信に立っていただくための運動である。その時寺がほんとうの寺となり、寺の繁盛、一宗の繁盛となる。然し単に一寺、一宗の繁栄のためのものでは決してない。それは「人類に捧げる教団」である。世界中の人間の真の幸福を開かんとする運動である。」と、世界中の人類に対し宗門の再興を誓い宣言することを持って始められた運動が真宗同朋会運動です。
その運動とは、宗門が七百年間宗祖聖人の威徳の上であぐらをかき、安逸をむさぼってきた教団であったという反省と懺悔に基づく自己批判から出発し、世界中の人間の真の幸福を開かんと願い、人類に捧げる教団へと変化していくことを誓いはじめられた信仰の復興運動です。
具体的には、形骸化し聞法道場としての機能を果たしていない寺院が、その機能を取り戻し、親鸞聖人の教えを伝え学ぶ施設へと転換することが求められ、各寺院やその地域等に「同朋の会」という聞法の会を開設することが進められました。また、運動を推進する人材育成も同時に進められ、育成員(僧侶)や推進員(門信徒)という制度を設けると共に、人材育成のための各種研修会等が教団を上げて行われました。