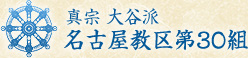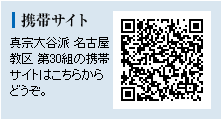仏教の基礎:釈尊の生涯
3. 釈尊の生涯
3-3 出家
釈尊は29才で出家しました。出家とは、仏教の専売特許ではなく、当時のインドではバラモン教以外の宗教家たち(シュラマナ)が一般に行っていました。また、インドでは一般に「四住期」、すなわち「学生期」(20才まで)「家長期」(40才まで)「林棲期」(60才まで)「遊行期」(それ以後)というライフサイクルが理想と考えられていました。釈尊は、家長期をまっとうせずに、いきなり遊行期に突入したのです。(林棲は引退ではありますが、出家ではありません。)
3-3-1 四門出遊
釈尊の出家の動機を物語る逸話として、「四門出遊」がよく知られています。大阪教区のサイトでこの話の概要が紹介されていますので、御存知でなければ、ぜひお読み下さい。
もちろん、これがそのまま史実であったとはいえません。しかしながら、老・病・死の実態を目の当たりにして、大きな衝撃を受けたということは、ありうる話です。ただ、青年になるまで老人や病人や死人を見たことがなかった、それらを城外に出て初めて見た、というのはかなり不自然です。いくら過保護に育てられたとしても。
インドの城というのは、日本のように大名・武士の居住区ではなく、街全体を城壁で囲って異民族・異部族からの侵攻に備えたものをいいます。そして城内には、ブラーフマナやクシャトリアだけでなく、ヴァイシャまで住んでいたはずです。では城外に住んでいたのは、といえば、シュードラしかありません。釈尊が目の当たりにしたのは、ふつうの老人・病人・死人ではなく、被差別階級の老人・病人・死人、すなわち悲惨な現実の中にうち捨てられた老・病・死であったとすれば、釈尊の受けた衝撃にも理由があることになります。
そしてシュラマナの姿を見て、自分もそのようになりたいと思ったとすれば、それはシュラマナの中に、真に自由な生き方を見出したからだと思われます。
釈尊はのちに、次のように述懐しています。
「愚かなる者は、自ら老いる身でありながら、かつ未だ老いを免れることを知らないのに、他人の老いたるを見ては、おのれのことはうち忘れて、厭い嫌う。考えてみると、わたしもまた老いる身である。老いることを免れることはできない。それなのに、他の人の老い衰えたるを見て厭い嫌うというのは、私にとって相応しいことではない。比丘たちよ、わたしはそのように考えたとき、あらゆる青春の誇りはことごとく断たれてしまった。(以下、病と死についても同じフレーズが続く。)」(『アングッタラ・ニカーヤ』3:38より、増谷文雄訳)
ここに仏教の原点を見出すことができます。まず、老・病・死の現実を明確に観察すること、それらを見て見ぬふりをしないことが第一。そして、それらが我が身に避けられないことを認識した上で、ではどうすればよいのか、と思慮するのです。釈尊は、シュラマナとして生きることにより、その回答を見つけたいと思われたのでした。
3-3-2. 出家のもつ意味
「その時、わたしはまだ年若くして、漆黒の髪をいただき、幸福と血気とにみちて、人生の春にあった。父母は私の出家を願わなかった。私の出家の決意を知って、父母は慟哭した。だが私は、髭と髪を剃り落とし、袈裟衣をまとい、在家の生活を捨てて、出家の修行者となった。」(『マッジマ・ニカーヤ』26より、増谷文雄訳)
出家とは、文字どおり家・家庭を捨てることです。このようなあり方は、俗世間の価値観や道徳を超越することを意味します。インドでは出家に寛容な風土がありましたが、中国や日本では出家は国家によって厳しく統制されました。それは、仏教のもつ世俗超越性が警戒されたからです。
剃髪にもまた、重要なメッセージが込められています。今日では、「虚飾をそぎ落とす」という意味に考えられていますが、それだけではありません。当時のインド社会では、ブラーフマナは、どんな罪を犯しても殺されることはなく、死刑の代わりに剃髪して追放されました。つまり、剃髪するとは、罪人のようになって社会から捨てられる、という生き方を自らの意思で選ぶということなのです。もっとも、釈尊や仏弟子達が剃髪したのは2ヶ月から4ヶ月に一度程度だったようです。したがって、スキンヘッドの時期はごく短期でした。剃髪したすがたの仏像が無いのもそのためです。
また袈裟はサンスクリット語の「カシャーヤ」の音訳ですが、意味は「混濁色」(カーキ色、暗灰色)で、袈裟衣とは「糞掃衣」、すなわち価値や使い道が無くなり捨てられたぼろ布、汚物を拭うくらいしか用のなくなった端布を縫製した衣を意味します。袈裟が形式化して華美になったのは、中国や日本で出家者が儀礼に関わり始めて以後のことです。
教心寺 釋眞弌