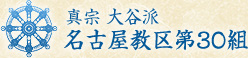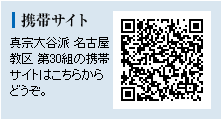仏教の基礎:釈尊の生涯
3. 釈尊の生涯
3-4 シュラマナとして
出家した釈尊が最初に向かったのは、ラージャグリハ(王舎城)でした。現代インドのラージギルです。当時のインドにおける最強国であるマガダ国の首都として、ラージャグリハは政治・経済・文化の中心地であり、多くの宗教家や思想家が住んでいました。
3-4-1 禅定を究める
釈尊がはじめに指導を仰いだのは、アーラーダ・カーラーマ という名のシュラマナでした。仏典の伝えるところによれば、彼が教えたのは、「無所有処」という境地に達するための瞑想(禅定)であったとのことです。これは、今日の体系化された仏教が「九次第定」と呼ぶところの、9段階の境地の第7番目に相当します。「無所有処」とは、 「何ものも真実には存在せず、見る自分(主体)と見られるもの(客体)の区別もない」という境地をいうとされています。すなわち「無の境地」のことです。
釈尊はこの境地にすみやかに達することを得ましたが、これに満足することはできませんでした。そこで、次に師事したのがウドラカ・ラーマプトラで、ここでは「非想非非想処」の境地について学びました。これは「意識(精神作用)があるのでもなくないのでもないという境地」を意味し、「九次第定」でいえば、第8番目に位置します。そしてこの境地にも速やかに達することを得たけれども、これに満足することはできなかった、と仏典は伝えています。
ここで「九次第定」とは、具体的には、初禅・第二禅・第三禅・第四禅・空無辺処定・識無辺処定・無所有処定・非想非非想処定・滅尽定を指します。もちろん、アーラーダ・カーラーマ 自身は無所有処を最高の境地と考え、ウドラカ・ラーマプトラ自身は非想非非想処を最高の境地と考えていたことは間違いありません。しかし釈尊がそれらに満足しなかったことから、更に高次元の境地があるはずと考えた後代の仏弟子が上記のように体系化したのです。おそらく釈尊自身は、そのような体系化は考えていなかったでしょう。
いずれにしても釈尊は、このような境地が自らの求めることとは違うことに気づいたのです。釈尊は後に、瞑想(禅定)を修行の方法として重視しましたが、それはあくまでも手段としてであり、ある境地に達することが悟りではないことに注意する必要があります。
3-4-2 修定主義の問題点
このような禅定をもってある境地に達することを目的とする考え方を「修定主義」といいます。その特徴は、次のようにまとめられます。
「修定主義というのは、精神を肉体の外に抽出しようとするもので、精神の陶冶に眼目をおき、精神を統一鎮静し、精神の奔放な活動である邪念を制御して、肉体とのかかわりから起こる物質的欲望の発動を抑え、平静な精神的至福の境地に入ることを念願する。つまり、われわれの邪念の根源である意識を滅ぼすことによって、絶対空無の境地に入ろうとする。」(山口益「仏教思想入門」)
釈尊はなぜここで満足することができなかったのでしょうか。第一に考えられることは、瞑想に入って意識・邪念を滅することに成功しても、それはあくまでも瞑想中だけのことであり、そこから出ればけっきょく元に戻ってしまうという、単純な事実です。
第二は、意識を滅ぼすことによって、邪念とともに感動する心や慈しむ心も失ってしまうではないか、という問題点です。これでは「産湯と共に赤子を流す」ことになってしまいます。無心の状態になることがほんとうに望ましいことなのでしょうか。これでは植物と変わらないのではないでしょうか。
第三に、仏教においては「身心不二」ということをいいますが、肉体と精神とは一体となって人間を形成しているわけですから、精神なき肉体、肉体なき精神は考えられません。つまるところ、アーラーダ・カーラーマ やウドラカ・ラーマプトラの誤りは、霊肉二元論的な発想にあったといえます。
天台宗の祖である隋の天台智・(Zhiyu、538-597)は、「止観」(=シャマタ・ヴィパシャナ=禅)ということを重視しましたが、精神作用を止滅すること「止」だけでは意味がなく、「観」すなわち正しい智慧となって働かなければならない、と説明しています。
とはいえ、アーラーダ・カーラーマ とウドラカ・ラーマプトラは、釈尊にとっては禅定の方法を伝えてくれた恩師であることにちがいはありません。後に釈尊は悟りを開いた時に、それを二人の恩師に伝えようとしました。二人はその時すでに逝去していたので実現しませんでしたが、「二人ならば自分のさとりを理解してくれるはず」と釈尊は考えたのです。
3-4-3 苦行生活へ
修定主義にあきたらなかった釈尊が次に目指したのは、苦行でした。苦行は、インドでさかんに行われていた修行で、現代でも多くの苦行者がいます。釈尊が実行した苦行は前例をみないほどの激しいもので、絶食・不眠・止息・糞尿食などを6年間も続けました。
釈尊はなぜそのような行に挑んだのでしょうか?修定主義が邪念の根源を精神に求めたのに対し、苦行主義は逆に、邪念の根源を「不浄なる肉体」に求めます。その肉体を徹底的に痛めつけることにより、精神を肉体から解放してやろうと考えたのだと思われます。しかし結果は、精神の輝きをえられるどころか、意識が混濁し朦朧としただけのことでした。
では、苦行はまったくの無益だったのでしょうか。釈尊は後に、修行方法として禅定は取り入れても苦行は取り入れていません。むしろ、「苦楽中道」といって、苦行主義も快楽主義も否定されています。しかしながら、単に無益であれば、苦行生活を6年間も続けたのはなぜか、という問題が残ります。おそらく、釈尊は苦行の中で邪念や欲望がある程度コントロールできることを学んだのだと思われます。苦行自体は悟りに至る道ではありませんが、釈尊自身にとっては必要不可欠な道程だったのでしょう。
いずれにしても、釈尊は苦行を捨てる決心をしました。そして付近の村人から乳粥(パサーヤ)の施しを受け、体力を回復させていきます。それまで釈尊と苦行を共にしてきた5人の仲間は、「彼は堕落した」と失望して他所へ移って行ってしまいました。
教心寺 釋眞弌